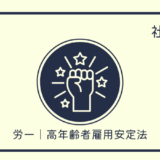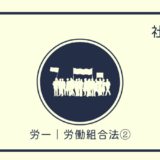この記事では、労働組合法から次の事項を解説しています。
- 労働組合法の目的
- 正当な争議行為についての免責
- 労働組合法における「労働者」
- 労働組合法における「労働組合」
- 労働協約
記事中の略語は次の意味で使用しています。
- 法 ⇒ 労働組合法
- 労調法 ⇒ 労働関係調整法
社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。
当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。
詳しくは免責事項をご確認ください。
労働組合法の目的等

はじめに、次の事項を解説します。
- 目的
- 正当な争議行為についての免責
社労士試験の勉強用に条文を載せておきます。
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
労働組合法の目的を箇条書きにすると、次のとおりです。
- 労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させる
- 労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する
- 使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成する
参考|労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する(憲法28条)
参考|労働三法
労働基準法、労働組合法、労働関係調整法を総称して「労働三法」といいます。
労働組合法では免責が定められています。
刑事免責
刑法35条の規定(法令又は正当な業務による行為は、罰しない)は、労働組合の団体交渉その他の行為であって法1条1項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用されます(法1条2項本文)
ただし、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはなりません(法1条2項ただし書き)
労働組合の争議行為が「正当」であるかは、その行為の主体、目的、手続きの正当性、手段を考慮して判断されます。
民事免責
使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することはできません(法8条)
(労働関係調整法はこちらで解説しています)
争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいいます(労調法7条)
労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態または発生する虞がある状態をいいます(労調法6条)
争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会または都道府県知事に届け出なければなりません(労調法9条)
また、公益事業に関する争議行為については、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会および厚生労働大臣(または都道府県知事)にその旨を通知しなければなりません(労調法37条1項、労調法施行令10条の4)
労働組合法の目的等の解説は以上です。
労働者
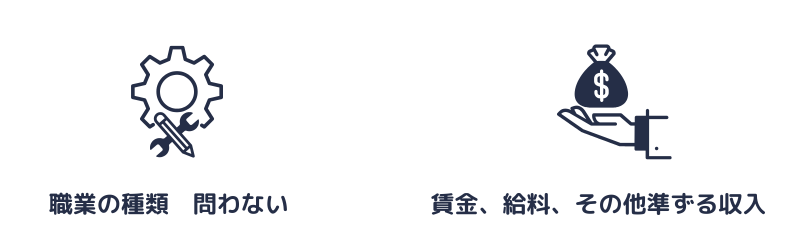
ここからは、労働組合法上の労働者について解説します。
労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいいます(法3条)
労働基準法における労働者(労基法9条)のように「使用される」や「賃金を支払われる」は要件ではないため、失業者や業務委託契約で働く者も「労働組合法上の労働者」になり得ます。
(業務委託契約については、最三小判 平23. 4.12 INAXメンテナンス事件などを参照)
実際問題としては、労働組合法上の労働者か否かの判断は簡単ではなく、次の判断要素を用いて総合的に判断すべきとされています(平成23年7月労使関係法研究会報告書)
基本的判断要素
- 事業組織への組み入れ
⇒労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか - 契約内容の一方的定型的決定
⇒契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか - 報酬の労務対価性
⇒労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するか
補充的判断要素
- 業務の依頼に応ずべき関係
⇒労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係にあるか - 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
⇒労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味で解することができるか、労務の提供にあたり日時や場所について一定の拘束を受けているか
消極的判断要素
- 顕著な事業者性
⇒労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者と見られるか
判断要素の考え方
次のように判断についての考え方も示されています。
- 基本的判断要素の一部が充たされない場合でも、直ちに労働者性が否定されないこと
- 各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定されるとまではいえなくとも、他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を肯定される場合もあること
- 各判断要素の具体的検討にあたっては、契約の形式のみにとらわれるのではなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断すべきである
労働組合法上の労働者性の具体的な判断基準については、下記のリンクをご参照ください。
参考|厚生労働省ホームページ(外部サイトへのリンク)|「労使関係法研究会報告書」について
労働組合

ここからは、労働組合法と労働組合の関係について解説します。
労働組合は労働者が組織する団体です。
ただし「労働者が組織する団体」 と「 労働組合法の労働組合」はイコールではありません。
労働組合法の「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいいます(法2条本文)
ただし、次の①~④のいずれかに該当するものは、労働組合法上の労働組合(以下、単に労働組合)となりません(法2条ただし書き)
- 使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
- 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの
- 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
- 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
ちなみに、上記①〜④に該当する団体(例えば、使用者の利益を代表する労働者で組織される団体)を組織することを否定する規定ではありません。
以降、①と②については個別に解説します。
(③と④については、労働組合の従たる目的としてなら行えます)
次のいずれかに該当する者の参加を許す団体(又はその連合団体)は、労働組合に該当しません(法2条1号)
- 役員
- 雇入、解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者
- 使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接するために、職務上の義務と責任とが労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者
- その他使用者の利益を代表する者
行政解釈によると、使用者の利益を代表すると認められる者の例が次のように示されています(昭和24年2月2日労働省発労第4号)
- 総ての会社役員、理事会又はこれに類似するものの構成員
- 工場支配人、人事や会計課の長、人事や労働関係に関する秘密情報に接する地位にある者
- 従業員の雇用、転職、解雇の権限を持つ者および生産、経理、労働関係、対部外関係、法規その他の専門的事項に関する会社の政策決定についての権限を持ちあるいはこれに直接参画する者
- 労務部(名称を問わずこれに該当する部課)の上級職員
- 秘書、人事や労働関係についての秘密の事務を取扱う者
- 会社警備の任にある守衛
「守衛」については、従業員に対する取締的権限を有せず、職務の内容が単に外来者の受付、施設の巡視等に止まるものは、一般に「使用者の利益を代表する者」に該当しないと解されています(昭和31年6月19日労収1045号)
令和の時代では、会社警備の任にある守衛が「従業員に対する取締的権限」を有するほうが珍しいかもしれません。
運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受ける団体(又はその連合団体)は、労働組合に該当しません(法2条2号)
ただし、次の①②③は「使用者の経理上の援助」に該当しないとされています(法2条2号ただし書き)
- 労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すこと
- 厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附
- 最小限の広さの事務所の供与
ちなみに、上記①②③はいずれも「不当労働行為」にも該当しません(法7条3号ただし書き)
実質的に考え、法5条を満たすことが「労働組合」の要件と説明されることもあります(一般的には、法5条の要件を満たした労働組合を「法適合組合」といいます)
労働組合は、労働委員会に証拠を提出して次のいずれもの規定に適合することを立証しなければ、労働組合法に規定する手続に参与する資格を有せず、かつ、この法律に規定する救済を与えられません(法5条1項本文)
- 法2条(労働組合法の労働組合に該当すること)
- 法5条2項(労働組合の規約に必要事項を定めていること)
ただし、上記の取扱い(法5条1項本文)は、組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いを不当労働行為として禁止する規定(法7条1号)に基づく個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではないとも規定されています(法5条1項ただし書き)
不当労働行為、労働委員会については、こちらの記事で解説します。
労働組合の規約
労働組合法による保護を受けるためには、労働組合の規約に、次の①から⑨までの規定を含める必要があります(法5条2項)
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 連合団体である労働組合以外の労働組合(単位労働組合といいます)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
- 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと。
- 単位労働組合にあっては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
- 総会は、少なくとも毎年一回開催すること。
- すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。
- 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
- 単位労働組合にあっては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。
(労働組合法の保護を受けるためには)上記⑧も規約に規定する必要があります。そのため、労働組合がストライキを実施するには、⑧の手続きを経る必要があります。
(労働組合法の労働組合を前提とする規定です)
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有します(法6条)
団体交渉をする権限を有する者には、労働組合の代表者のみならず、労働組合の委任を受けた者も含まれます。
労働組合の解説は以上です。
労働協約

ここからは、労働協約について解説します。
ごくごく単純化すると、労働協約とは、労働組合と企業との間で結んだ決まりごと(書面)です。
ちなみに、令和4年労使間の交渉等に関する実態調査によると、労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で労働協約を「締結している」は94.5%となっています。
参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|令和4年労使間の交渉等に関する実態調査 結果の概況
労働協約の効力の発生
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生じます(法14条)
- 労働協約の中に定められた労働条件その他労働者の待遇に関する基準は、労働協約の規範的部分といいます
- 規範的部分以外(例えば、労働組合活動、団体交渉、争議行為に関する事項)は、労働協約の債務的部分といいます
規範的部分については、労働協約は就業規則に優先します(労基法92条1項、同旨 昭和24年1月7日基収4078号)
労働協約に定める基準の効力
労働者の待遇に関する基準(規範的部分)については、次のように労働協約が優先します(法16条)
- 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。
- ①の場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。
- 労働契約に定めがない部分についても、同様とする。
- 労働協約には、3年をこえる有効期間の定めをすることができません(法15条1項)
- 3年をこえる有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間の定めをした労働協約とみなします(法15条2項)
- 有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によって相手方に予告して、解約できます(法15条3項前段)
有効期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定めがある労働協約についても、有効期間の経過後は、③と同様の手続きにより解約できます(法15条3項後段)
なお、③の予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にする必要があります(法15条4項)

労働協約は、原則として、労働協約を締結した労働組合の組合員(及び締結当事者である使用者、労働組合)にのみ適用されます。
原則に対する例外(労働協約の拡張適用)としては、「一般的拘束力」「地域的な一般的拘束力」が定められています。
一般的拘束力
一つの工場事業場(事業場は工場に限りません)に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一つの労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されます(法17条)
「一つの工場事業場」とは、一つの企業が数個の工場事業場を有する場合は、その企業内の個々の工場事業場をいいます(昭和29年4月7日労発111号)
なお、労組法17条の適用については、「労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、労働協約の規範的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが相当である」と示した判例があります(最三小判 平成8年3月26日 朝日火災海上保険(高田)事件)
地域的な一般的拘束力(労働協約の地域的拡張適用)
一つの地域において従業する同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適用を受けるに至ったときの定めです。
上記の場合、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことを決定することができます(法18条1項)
上記の決定は、当該労働協約の当事者の双方または一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、行われます(法18条1項)
厚生労働大臣が決定した事案については、下記のリンクをご参照ください。
参考|厚生労働省ホームページ(外部サイトへのリンク)|労働協約の地域的拡張適用について厚生労働大臣が決定した事案
(労働組合基礎調査の解説はこちらの記事に移行しました)
解説は以上です。
社労士試験では、毎年のように労働組合法からの出題がみられます。
繰り返し出題されている論点もありますので、少なくとも過去問と同じ論点は解けるようにしてください。
実務におかれましては、専門家の意見や専門書なども参考にしてください。
(参考資料等)
厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html
- 労働組合法
- 労働関係調整法
- 平成23年7月25日政発725001号(労働組合法上の労働者性の判断基準について)
- 昭和24年2月2日労働省発労第4号(使用者の利益を代表する者)
- 昭和31年6月19日労収1045号(守衛、組合専従者に対する就業規則の適用、メーデー参加者に対する賃金支給等)
- 昭和29年4月7日労発111号(一の工場事業場)
厚生労働省ホームページ|労働組合
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/roudoukumiai/index.html
厚生労働省ホームページ|労働協約の拡張適用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/roudoukumiai/index_00004.html